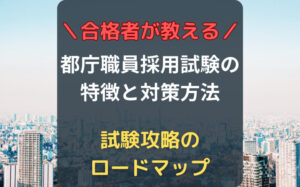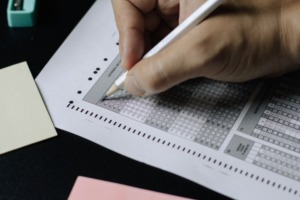- 公務員試験対策をしようと思うけど、予備校の選び方がわからない…
- 予備校を選ぶ際に知っておくべき知識や注意点はあるのかな…
- 本当におすすめの具体的な公務員試験予備校を教えてほしい!
このような疑問にお答えします。
この記事を書く私も実際に公務員予備校を利用して、民間企業から公務員への転職を果たしました。
本記事では、予備校を選ぶ際のポイントからおすすめの公務員予備校までご紹介します。
記事を読み終えれば、自分に合った予備校を見つけられますので、ぜひ参考にしてください。
\最終合格率85% 無制限サポート付きで安心/
おすすめの公務員予備校3選



それでは、公務員試験対策におすすめの3つの予備校を紹介します。
- EYE公務員試験予備校
- クレアール
- 資格の学校TAC
数ある公務員予備校の中から、3校+αに厳選しました。予備校の比較表は以下のとおりです。
| EYE公務員試験予備校 | 資格★合格クレアール | 資格の学校TAC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 予備校 |    |     |  | ||
| 価格 | 〇 | ◎ | △ | ||
| 実績 | 〇 | 〇 | ◎ | ||
| 面接対策 | ◎ | 〇 | ◎ | ||
| 専門記述対策 | ◎ | 〇 | ◎ | ||
| 講義時間数 (スタンダートコースの場合) | 約518時間 | 約350時間 | 約460時間 | ||
| 個別サポート | ◎ | 〇 | ◎ | ||
| 特徴 | 少人数制で講師の面倒見の良さに定評のある予備校。高い合格実績も出している。 | 通信学習の専門スクール。「非常識合格法」を学習コンセプトにしている。 | 毎年多数の最終合格者を輩出する大手予備校。大卒レベルの公務員試験に強い。 | ||
| 公式HP | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
①EYE公務員試験予備校
EYE公務員試験予備校は、受講生に対する手厚い面倒見で定評のある予備校です。
東京都内の3ヶ所に校舎があり、通信と通学どちらにも対応しています。
| カリキュラム (シンプルコース(教養+専門)) | ①合格方法確立講義・入学時カウンセリング ②入門講座 ③基礎数的処理 ④専門科目 ⑤教養科目 ⑥時事科目 ⑦理解度確認テスト ⑧論述試験対策 ⑨SPI対策 ⑩面接試験対策 |
| 料金 | 267,800円(税込) |
| 講義時間数 | 約518時間(全565コマ:1コマ55分講義) |
| 合格実績 | 【2022年度】最終合格率:70.6%(221名/313名) |
| サポート体制 | ・対面、オンラインでの個別相談 ・LINEでの学習相談・週間学習実績表へのアドバイス |
| 運営会社 | 株式会社グローバルアイ |
\最終合格率85% 無制限サポート付きで安心/
メリット
- 少人数制で担任・講師との距離がすごく近い
- 週間学習実績表を提出することで学習アドバイスがもらえる
- 高い合格実績があり安心して学習できる
デメリット
- 毎月の入校定員がある
- 校舎数が少ない
受講料金
主なコースの料金は以下のとおりです。プレミアムコースには個別授業が付いています。
| コース | 受講料(税込)(大学生協等・代理店割引適用後) |
|---|---|
| シンプルコース(教養+専門) 【WEB通信講座】 | 267,800円 |
| シンプルコース(教養+専門) 【通学講座】 | 288,800円 |
| プレミアムコース(教養+専門) 【WEB通信講座】 | 317,800円 |
| プレミアムコース(教養+専門) 【通学講座】 | 338,000円 |
※適宜割引キャンペーンも実施しているため、詳しい金額は公式ホームページでご確認ください。

EYEがおすすめな人
- 少人数制で面倒見の良さを重視したい人
- 受験勉強が苦手で途中挫折しないか不安な人
- 他の予備校を利用して公務員試験に合格できなかった人
EYEは受講生人数を制限しており、一人ひとりに寄り添ったサポートをしてくれます。
大人数の予備校は相談しづらくて苦手と感じる方には特におすすめです。




実際に私もEYEのシンプルコース(WEB通信講座)を利用しました。
\PDF版はメール登録後すぐもらえる!/
>>【EYE公務員予備校の評判を検証】料金や特徴、合格体験記もまとめて紹介



②クレアール
クレアールはWebに特化した通信学習の専門スクールです。
学習コンセプトである「非常識合格法」により、合格必要論点を効率的に学べます。
| カリキュラム (東京都Ⅰ類B(行政・一般方式)コース) | ①教養ベーシック講座 ②専門ベーシック講座 ③記述対策講座 ④時事対策講座 ⑤人物試験対策講座 ⑥答練 ⑦模試 |
| 料金 | 260,000円(税込) |
| 講義時間数 | 約350時間 |
| 合格実績 | 【2022年度】:合格者325名 【2021年度】:合格者309名 |
| サポート体制 | ・担任サポート ・質問サポート |
| 運営会社 | 株式会社クレアール |

メリット
- 割引利用により受講料が低価格になる
- 非常識合格法により短期間で効率的な学習ができる
- 安心保証プランで受講期限を1年間延長できる
デメリット
- 対面での面接練習ができない
- 通信講座のみで通学講座はない
受講料金
主なコースの料金は以下のとおりです。
| コース | 受講料(税込) |
|---|---|
| 1年合格 行政系公務員併願総合コース | 300,000円 |
| 1年合格 地方上級スタンダードコース | 285,000円 |
| 1年合格 地方上級ベーシックコース | 250,000円 |
| 1年合格 東京都Ⅰ類B(行政・一般方式)コース | 260,000円 |
| 1年合格 特別区Ⅰ類(事務)コース | 260,000円 |
※適宜割引キャンペーンも実施しているため、詳しい金額は公式ホームページでご確認ください。
クレアールがおすすめな人
- オンラインで自分のペースで学習を進めたい人
- 割引を利用して、なるべく予備校費用を抑えたい人
- 試験準備が不安で受講期限を1年間延長しておきたい人
\期間限定割引キャンペーン実施中!/
③資格の学校TAC
資格の学校TACは、毎年多数の最終合格者を輩出している、言わずと知れた大卒レベルの公務員試験に強い大手予備校です。
| カリキュラム (総合本科生 Lite) | ①オリエンテーション基本講義 ②基本演習傾向分析講義 ③一般知識講義 ④選択講義 ⑤論文対策 ⑥専門記述対策 ⑦総合演習 ⑧教養実力確認テスト ⑨試験対策ゼミ ⑩公開模試 ⑪時事対策 ⑫面接試験対策 |
| 料金 | 286,000円(税込) |
| 講義時間数 | 約460時間(全152回、1講義180分)=456 |
| 合格実績 | 【2022年度】:実合格者2,843名 |
| サポート体制 | ・質問、相談制度 ・面接サポート ・公開模試 ・添削指導 ・学習フォロー制度 |
| 運営会社 | TAC株式会社 |

メリット
- 高い合格実績があるため安心して学習できる
- 専任の担任講師が受講生一人ひとりを合格までサポート
- 公開模試を無料で受験できる
デメリット
- 他の予備校よりも受講料が高い
受講料金
主なコースの料金は以下のとおりです。
| コース | 受講料(税込) |
|---|---|
| 総合本科生(Web通信講座) | 352,000円 |
| 総合本科生 Lite(Web通信講座) | 286,000円 |
| 主要科目本科生(Web通信講座) | 286,000円 |
※適宜割引キャンペーンも実施しているため、詳しい金額は公式ホームページでご確認ください。
資格の学校TACがおすすめな人
- 中小よりも大手の予備校がいい人
- 合格実績を重視したい人
- 受講料が多少高くても問題ない人
\圧倒的な合格実績で安心 /
公務員予備校選びに必要な5つのポイント



ここでは私が実際に予備校を選んだ経験をもとに、絶対に押さえておくべきポイントを紹介します。
- 合格者を多数輩出している実績がある
- フォロー制度など学習支援が充実している
- 面接対策のサポート体制が整っている
- 受験予定の試験に対応している
- 価格が適正である
①合格者を多数輩出している実績がある
1つ目は実績を出していることです。
合格者が多い予備校は信頼度も高く、合格可能性も高いと考えられます。
せっかく予備校を利用するなら、合格しやすいところの方が安心でしょう。
もちろん大手予備校は受講生も多いため、高い実績を持っています。
しかし、中小の予備校でも受講生一人ひとりと向き合い、毎年着実に合格者を増やしているところも多いです。
合格者数だけではなく、合格率も見ることで本当の実績がわかります。
各予備校の実績は事前にチェックし、少なくとも実績を公表していない予備校は避けましょう。
②フォロー制度など学習支援が充実している
2つ目は、個別相談などのフォロー制度が充実していることです。
試験に合格するためには、不安に打ち勝ち最後まで学習を継続することが欠かせません。
とはいえ、学習を続けていれば、ちょっとした質問や相談したいことが出てくるでしょう。
講師や先輩に気軽に相談できる環境があれば、すぐに疑問や不安を解消できて、学習もスムーズに進められます。
多くの予備校では、質問や相談できる体制を整えているため、基本的には問題ありません。
ただフォロー内容が予備校によって多少異なるため、事前に確認しておくといいでしょう。




勉強は孤独な戦いでもあるため、一人で悩みを抱えずにすぐに相談することが大切です。
③面接対策のサポート体制が整っている
3つ目は面接対策のサポートが充実していることです。
公務員試験は面接試験が最大の関門であり、十分に対策する必要があります。
予備校で面接シート添削や模擬面接などを確実に受けられる体制になっているか確認しましょう。
予備校によっては対面だけでなく、オンラインでの模擬面接も実施しています。
利用できるものは利用し尽くして、入念に面接対策を行いましょう。
なお試験本番は対面での面接であるため、一度は対面で模擬面接を行うのがおすすめです。
④受験予定の試験に対応している
4つ目は受験予定の試験に対応したカリキュラムがあることです。
例えば、都庁I類B試験を受けるなら専門記述対策が盛り込まれている必要があります。
予備校のパンフレットには、各講座がどの試験に対応しているか記載されているので、自分が受験する試験に対応したものか確認しましょう。
また講座を選ぶ際は、オーバースペックにならないよう注意が必要です。
多くの試験に対応しているコースだと、必要以上の内容になっている可能性もあります。
効率よく合格を目指すためにも、自分の受験する試験に絞り込んだ必要最低限のカリキュラムを選びましょう。
⑤価格が適正である
5つ目は価格が適正であることです。
適正かどうかは、人それぞれ予算が異なるため一概にはいえません。
とはいえ、なるべく費用は抑えたいところ。期間限定キャンペーンや各種割引を最大限利用しましょう。
大手予備校は価格が高い傾向にある一方で、通信特化の予備校は低価格なことが多いです。
一般的な公務員予備校の相場は約25〜30万円です。
多くの予備校では講義やテキスト、面接対策などがセットになっており基本的に追加費用は発生しません。
価格が講義内容やサポート環境と見合ったものかを考慮して、予備校を選びましょう。
\最終合格率85% 無制限サポート付きで安心/
公務員予備校の通信講座と通学講座の違い



予備校を利用する際に、通信と通学どちらを選べばいいか迷うかもしれません。
結論から言うと、社会人なら通信講座一択です。
通信講座と通学講座のメリットとデメリットを以下にまとめました。
| 通信講座(オンライン) | 通学講座 | |
|---|---|---|
| メリット | ・自分のペースで学習できる ・学習コストを抑えられる ・場所を選ばずに学習できる | ・直接質問や相談ができる ・対面で講義を受けられる ・学習仲間を作りやすい |
| デメリット | ・自分で時間を確保して学習を進める必要がある ・モチベーション維持が難しい ・質問や相談に多少の時間がかる | ・決められた時間に学習する必要がある ・移動コストが発生する ・学習ペースが制約される |
通信の方が通学よりも時間を有効に活用できるのが最大のメリットです。




オンラインをベースにして、模擬面接時など必要に応じて、校舎を利用するといいでしょう。
公務員予備校を利用した方がいい理由3選







予備校を利用するとなるとお金もかかるから、本当に利用すべきか迷うな…




私も迷って独学から始めましたが、結局予備校を利用しました。
そこで、以下では公務員予備校を利用した方がいい理由を3つ紹介します。
- 面接や論文試験対策ができる
- モチベーションが維持しやすい
- 試験情報が入手しやすい
①面接や論文試験対策ができる
1つ目は面接や論文対策ができることです。
公務員試験では、面接と論文は避けては通れません。
特に面接試験は教養試験や専門試験とは違い、一人で対策するには限界があります。
面接と論文を上達させるためには、フィードバックをもらうことが欠かせません。
もちろん、スポット的に面接と論文だけ予備校を利用するのもいいでしょう。
しかし、コース単位で受講した方が模擬面接や論文添削も無制限にできるため、結果的にお得になる可能性もあります。
予備校は長年の実績や情報の蓄積により、効率よく学習できるカリキュラムを組んでいます。
時間節約のためにも、予備校を利用するのがおすすめです。
②モチベーションが維持しやすい
2つ目はモチベーションを維持しながら学習できることです。
公務員試験へ合格するためには、長期間学習を続ける必要があります。
独学の場合は、自分で学習計画を立ててやり抜いていくことが不可欠です。
学習が得意で自己管理に自信がある方なら問題ないでしょう。
しかし、多くの人にとって、サポートなしで一人でもくもくと学習を継続するのは困難です。
実際に私もモチベーションが上がらず、独学での学習を挫折した一人です。
誰かに相談できる環境があることは、思っている以上に学習の助けになります。
予備校を利用すれば、もれなく学習の相談や質問ができるサポートがついてきます。
学習のモチベーションを保つためにも、予備校の利用がおすすめです。
\最終合格率85% 無制限サポート付きで安心/
③試験情報が入手しやすい
3つ目は試験情報が手に入りやすいことです。
公務員試験は情報戦といっても過言ではありません。
例えば、試験の過去問や面接で聞かれる内容は必ず把握しておく必要があります。
予備校では、各試験の過去問や合格者の体験記など多くの情報を持っているため、簡単に情報を入手することが可能です。
実際に合格した先輩から直接話を聞くこともできるため、情報収集に困ることはないでしょう。
一方、独学の場合はネットや書籍の情報に頼らざるを得ません。
各試験の体験談など、本当に重要な情報はあまり公表されていないため、予備校に比べて情報量は少なくなります。
情報戦を制して最短で合格をつかむためにも、予備校の利用がおすすめです。
公務員予備校を選ぶときのよくある質問



公務員予備校はいつから通えばいい?
結論から言うと、なるべく早い方がいいです。
試験までの学習時間を長く確保するためです。
公務員試験へ合格するためには、余裕を持って1年、少なくとも6ヶ月の学習時間が必要とされています。
例えば、試験が5月の場合、前年の5月から予備校を利用し始めるのが理想です。遅くても前年の10月には利用を開始する必要があります。
試験日から逆算して、なるべく早く予備校に申し込みましょう。
事前に資料請求や個別相談をした方がいい?
結論から言うと、事前に資料請求や個別相談はするべきです。
予備校の利用前後でのギャップを減らすためです。
資料にはホームページにはない情報が掲載されている場合もあります。
事前に資料請求をして、カリキュラム内容や学習スケジュール、フォロー体制などを確認しておくといいでしょう。
不安なことや気になることがあれば、個別相談をして解消することも可能です。
個別相談はオンラインでも対応しているので、直接校舎へ行かずとも気軽にできます。
どちらも無料なので、やって損することはありません。
予備校選びに迷う場合は、まずは資料請求をしてみましょう。
\PDF版はメール登録後すぐもらえる!/
予備校に通うためのお金がない場合はどうすればいい?
結論から言うと、お金を借りることを検討してください。
なぜなら、お金が貯まるまで待つのは時間がもったいないからです。
方法の一つとしては、両親や親戚から一時的に借りることです。
公務員へ合格すれば最初のボーナスで一気に返済可能なことを示すことで、説得もしやすいでしょう。
親族から借りるのが難しい場合は、教育ローンを利用する方法もあります。




実際に私は教育ローンを使って予備校代を払い、入庁後にお金を返しました。
とはいえ、借金すること自体に多少の抵抗があるかもしれません。
しかし、時間は有限であり、だらだらと学習を進めるよりも覚悟を決めて取り組む方が、結果も出やすいです。
資金に余裕がない場合は、将来への投資と考えて、無理のない範囲で借金することも検討しましょう。
まとめ:おすすめ公務員予備校3選|試験対策はプロに任せるのが近道



最後にもう一度本記事の内容を確認しましょう。
おすすめの公務員予備校は以下の3つです。
【おすすめ公務員予備校3選】
- EYE公務員試験予備校
- クレアール
- 資格の学校TAC
【番外】アガルートアカデミー
予備校は公務員試験対策のプロ集団です。
本気で公務員試験への合格を目指すなら、プロに頼るのが定石であり一番の近道といえます。
予備校は多少の費用がかかるものの、試験対策に集中できる環境や手厚いサポートが得られるなど、メリットも大きいです。
将来への自己投資と考えれば、間違いなく必要な投資といえるでしょう。
まずは資料請求や個別相談を利用して、自分に合う予備校を探してみてください。
\最終合格率85% 無制限サポート付きで安心/