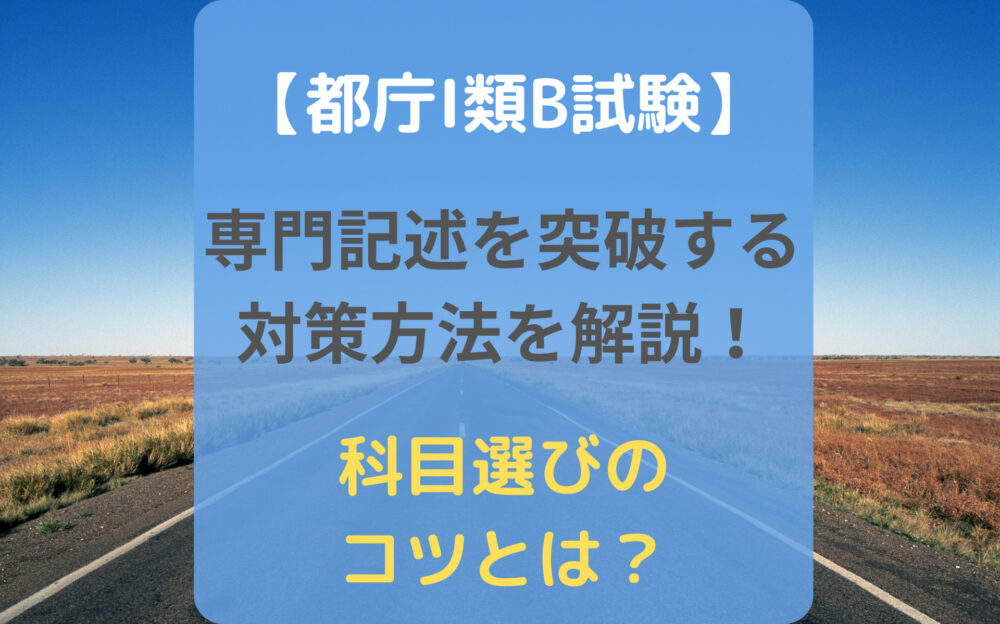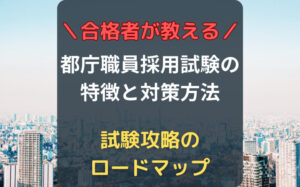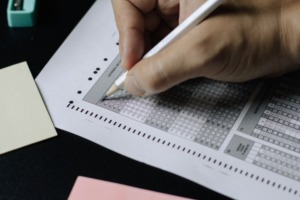- 都庁I類Bの専門記述試験で準備する科目の選び方がわからない
- 科目の具体的な選択例や選ぶ際のコツが知りたい。
- 都庁I類Bの専門記述試験を乗り越えるための対策方法を教えてほしい
今回は、こんな疑問にお答えします。
本記事の内容
- 都庁I類B専門記述で用意する科目数
- 専門記述の科目を選ぶポイント
- 専門記述の科目選択例と準備テーマ数
- 専門記述の合格ライン
この記事を書く私は民間企業で働きながら、都庁I類B専門試験に合格しました。
本記事では、私が実際に行った都庁I類B専門試験(行政)における科目の選び方や対策方法を紹介します。
都庁I類Bの専門科目選びや対策方法に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
\最終合格率85% 無制限サポート付きで安心/
都庁の専門記述試験とは



都庁I類B(行政)専門試験の概要は以下のとおりです。
| 試験内容 | 解答方式 | 試験時間 | 専門試験の出題範囲(行政) |
|---|---|---|---|
| 職務に必要な専門分野の記述式 | 10題中3題の選択回答 | 2時間 | 憲法、行政法、民法、経済学、財政学、政治学、行政学、社会学、会計学、経営学 |
各科目から1題出題され、1題あたり40分を目安に回答します。
>>【合格者が教える】都庁職員採用試験の特徴と対策方法|試験攻略のロードマップ
都庁専門記述の出題科目の選び方



では早速、都庁専門記述の出題科目の選び方を紹介します。
- 専門記述は出題科目から5つ選択する
- 専門記述の科目分野は分散する
- 専門記述の具体的な科目選択例
- 専門記述の準備に必要なテーマ数
専門記述は出題科目から5つ選択する
専門科目は最低でも5科目は用意しましょう。
なぜなら、毎年科目ごとの難易度が異なるためです。
3科目だけの場合、用意した科目の難易度が高くて対応できない可能性があります。
試験当日は問題を見た上で、自分が用意した5科目の中から書けそうなものを3つ選ぶといいです。
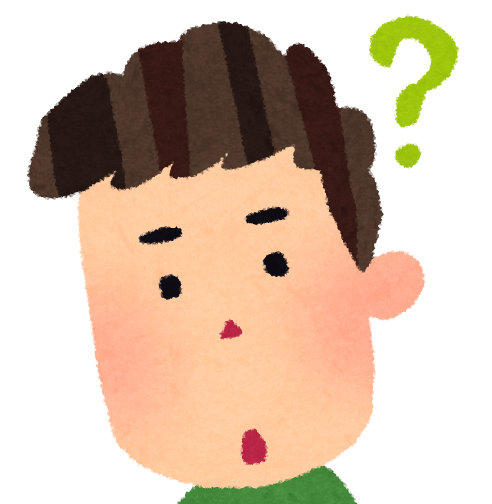
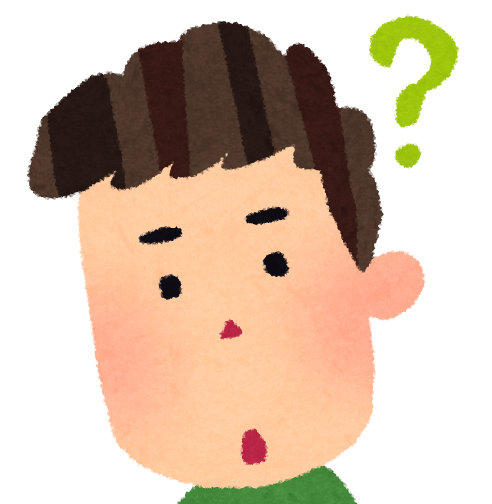
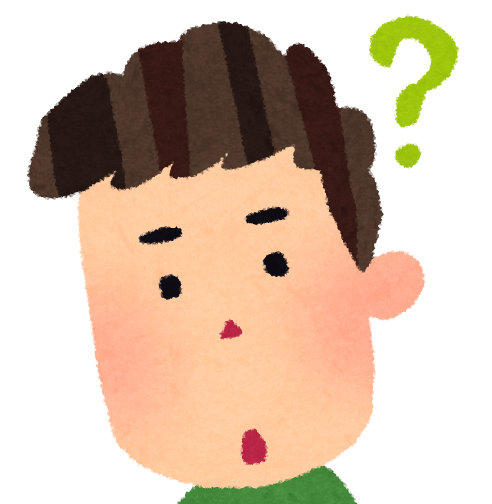
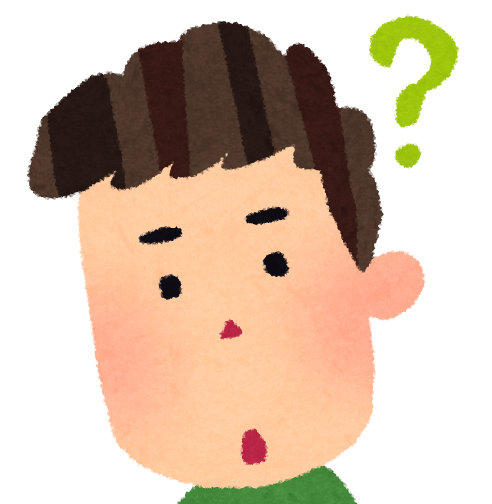
とはいえ、試験では3科目選べばいいのだから、3科目だけに絞って勉強するほうがコスパがいいのでは?
確かに、3科目に絞る方が準備の時間も削減できるため有効な戦略かもしれません。
ただ、用意した3科目どれか1科目でも難問や奇問が出題された場合、全く回答できないリスクがあります。
試験合格には、受験生が取れる問題を落とさず、平均点以上を着実に取ることが不可欠です。
リスクを避けるためにも、5科目準備して簡単な問題から3つ選べるようにしておきましょう。
専門記述の科目分野は分散する
準備科目は各分野からバランスよく選ぶことも大切になります。
リスクをできる限り減らすためです。
出題科目の分野はおおむね以下の3分野に分けられます。
- 法律系(憲法、行政法、民法)
- 経済系(経済学、財政学、会計学)
- 行政系(政治学、行政学、社会学、経営学)
バランスを考えて各分野の中から1〜2科目を選ぶといいでしょう。
とはいえ、各分野に集中して科目を選択する方が、関連する内容も多くて対策しやすいのではという意見もあると思います。
確かに、分野を絞るほうが勉強はしやすいです。
しかし、選んだ分野で難問が多かった場合、十分に回答できないリスクが高くなります。
専門記述試験では、簡単な問題を選んで、確実に点数を取ることが大切です。
そのため、選択科目の分野はなるべく分散してリスクに備えましょう。
専門記述の具体的な科目選択例
ここでは、具体的な科目の選択例を紹介します。
上記でも解説したとおり、科目分野のバランスを取ることを前提としています。
人それぞれ得意・不得意の科目が異なるため、自分の適正も加味して選ぶといいでしょう。
主な選択例を下記にまとめました。
バランスのよい選択例
- 憲法、経済学、財政学、政治学、行政学
- 憲法、行政法、財政学、政治学、社会学
- 行政法、経済学、財政学、行政学、社会学
おすすめはしませんが、リスクを取って効率的に学習したい方は、各分野に特化した選択でもよいでしょう。
主な選択例を下記にまとめました。
各分野に特化した選択例
| 法律系 | 憲法、行政法、民法、政治学、行政学 |
| 経済系 | 経済学、財政学、会計学、行政学、社会学 |
| 行政系 | 政治学、行政学、社会学、経営学、財政学 |
専門記述の準備に必要なテーマ数
合計75テーマ程度(5科目で各15テーマずつ)を用意することが必要です。
15テーマあれば、各科目における頻出分野を抑えられるため、本試験でも大部分の問題に対応できます。
なお、経済学の場合はミクロとマクロがあり範囲が広いため、各10ずつの合計20テーマは必要です。
そのため経済学を選択する場合は、他の科目を10題に減らして調整してもいいでしょう。
例えば、以下のとおりです。
| 選択科目 | 準備テーマ数 |
|---|---|
| 憲法 | 15 |
| 経済学 | 20(マクロ10、ミクロ10) |
| 財政学 | 10 |
| 政治学 | 15 |
| 行政学 | 15 |
| 合計 | 75 |
とはいえ、75テーマも用意できる時間や余裕がないよと思うかもしれません。
確かに、15テーマでも内容を網羅しつつ着実に理解する必要があるため、準備は大変です。
しかし、専門試験を通過するためには、多くの受験生が取れる問題を落とさず平均点以上を得点する必要があります。
そのため、最低でも各科目15テーマ、合計75テーマを目安に準備しましょう。
準備テーマ数を必要以上に増やすことはおすすめしません。
範囲を広げすぎると知識が浅くなり回答内容も薄くなるおそれがあるからです。
もちろん時間に余裕がある方や暗記が得意な方は、テーマ数を増やしても問題ありません。
なるべく論点をしぼって深い知識を身につけた上で、試験に臨みましょう。
都庁専門記述のおすすめ科目5選



ここでは私が実際に選んだおすすめの科目5つを紹介します。
- 憲法
- 経済学
- 財政学
- 政治学
- 行政学
①憲法
憲法はおすすめの科目の1つです。
おそらく中学や高校で一度は学んだ経験があるため、取っ付きやすい科目と言えるでしょう。
憲法は教養試験の社会科学にも関連するため、学習しておいて損はありません。
準備する論点もほとんど決まっているため、対策しやすい科目の一つです。
法律系から選ぶなら憲法を選んでおけば、間違いないでしょう。
②経済学
経済学も比較的対策しやすくおすすめです。
ミクロ経済とマクロ経済の2科目分のボリュームがあり敬遠する人もいますが、逆に狙い目とも言えるでしょう。
何より図を用いて説明する問題が出た場合に、効率的に答案を埋められるメリットがあります。
さらに、教養試験の社会科学(経済)対策にもなるため、一石二鳥です。
経済に苦手意識がある方を除いて、選択することをおすすめします。
③財政学
経済学を選択するなら財政学もおすすめです。
論点数が少なく対策しやすいからです。
経済学に比べて表や計算を使うことは少なく、どちらかと言うと暗記系の科目といえます。
経済学と重複する分野や教養試験の社会事情と関連性もあり、学習負担も少ないです。
そのため、財政学を経済学とセットで選択しておくといいでしょう。
④政治学
政治学は個人的には一番おすすめです。
論点もある程度決まっており、学習しやすく対策も比較的簡単です。
政治学は行政学と内容が重複する箇所もあるため、一緒に学習すると効率的です。
実際に私も本試験で政治学と行政学を選択しました。
特段の理由やこだわりがなければ、政治学を選択しておくといいでしょう。
⑤行政学
行政学も政治学と同様におすすめ科目の1つです。
対策すれば確実に得点源になる科目といえます。
政治学と同様に論点を整理して、暗記すれば試験対策としては問題ありません。
さらに、専門択一の問題も解いて知識の幅を広げつつ、理解を深めておきましょう。
政治学と行政学の2トップで確実に得点を取りにいく戦略が有効です。
避けるべき科目2選
ここではなるべく避けた方がいい科目を紹介します。
民法
民法は大学などで学んだ人以外は避けるべきでしょう。
範囲が広く内容の理解にも時間がかかるためです。
例えば、特別区の専門試験における民法は、以下のとおり2科目分として出題されています。
- 民法①[総則・物権]
- 民法②[債権・親族・相続]
2科目分のボリュームを1科目として学習するのは、コスパが悪いです。
経済学も2科目分ありますが、難易度は民法の方が圧倒的に高いでしょう。
学習経験者を除き、民法は選択しないことをおすすめします。
会計学
会計学の選択もおすすめしません。
公務員試験の中でもマイナーな科目であり学習に対するパフォーマンスが悪いからです。
実際に、会計学は国税専門官など一部の試験のみで出題され、多くの公務員試験では出題されません。
簿記の学習経験者であれば選択の余地はあるものの、公務員試験対策として会計学を学ぶのはおすすめしません。
都庁専門記述試験の対策方法5ステップ



それでは、都庁専門記述試験の対策方法を5ステップで紹介します。
- 専門択一の勉強をする
- 出題テーマをピックアップする
- 準備答案を作成する
- 準備答案を覚える
- 模擬試験を受ける
①専門択一の勉強をする
まずは専門択一の問題を解いて学習を進めます。
答案作成に必要な基礎的知識を身につけるためです。
知識を着実に身につけるためには、アウトプットしながらインプットするのが効率的です。
ひとまず問題集を1周して、出題範囲の内容を網羅するといいでしょう。
②出題テーマをピックアップする
次は過去問を参考にしながら出題テーマを予想します。
論点をしぼって効率的に学習を進めるためです。
例えば、直近3年間で出題されたテーマは、出題される可能性が低いといえます。
また過去問を見ていると、同じようなテーマが一定の間隔で出題されていることがわかるでしょう。
とはいえ、予想を当てることに焦点をおいてしまうと、外れた時の代償が大きいです。
そのため、過去出題されたテーマの中から、なるベく多くのものを網羅しておきましょう。
③準備答案を作成する
上記で抽出したテーマをもとに模範答案を作成していきます。
具体的には、参考書の内容を引用しながらレジュメを作っていくイメージです。
1つのテーマに対して、1つの答案をまとめていきましょう。
想定問題と答案をノートの見開きでまとめると、見やすくなります。
例えば、以下のような構成がおすすめです。

答案作成はとても時間と労力がかる大変な作業です。
しかし、良質な答案の準備ができるかが、合否を分けると言っても過言ではありません。
手を抜かずに地道にやり抜きましょう。
④準備答案を覚える
模範答案を作り終えたら、ひたすら答案を覚えていきましょう。
覚え方は、紙に書いたり、声に出して読み上げたり、自分に合った覚えやすい方法でいいでしょう。
なお答案を暗記すること以上に、内容の理解が大切になります。
覚えた答案を試験で再現する必要がある一方で、実際に模範答案を一字一句覚えるのはほぼ不可能だからです。
また、問題によっては用意した答案内容を臨機応変にアレンジする必要もあります。
そのため、内容を十分理解しながら、答案を覚えるようにしましょう。
⑤模擬試験を受ける
最後の仕上げとして模試を受けましょう。
模試を受験することで学習内容の理解度がチェックできます。
具体的には、都庁試験に対応した専門記述が含まれる模試を申し込みます。
試験当日と同じ形式で実施されるため、時間配分などのシミュレーションもできておすすめです。
さらに模範解答をゲットでき、回答内容への添削とアドバイスももらえます。
模試は正直なところ受けない理由がありません。




準備不足で受けても損はしないため、ぜひチャレンジしてみることをおすすめします。
>>【受けないと損】都庁受験者におすすめの公務員模試を解説【3つでOK】
都庁専門記述の合格ライン



では最後に、都庁専門記述の合格ラインについて解説します。
専門記述に足きりはない
まず前提として専門記述試験には足切りはありません。
教養試験と違って、明文化されていないためです。
ただし足切りがないとはいえ、最低限答案の半分以上を埋めることは必須と言えるでしょう。
答案内容に関する採点は、採点者によって差が出ることもあります。
ただこちらではコントロールできないので考えても仕方ありません。
答案を書き切って、あとは天命を待つしかないです。
採点者から実質的な足切りがされないように、十分な対策をしましょう。
合格ラインに必要な文字数
合格に必要な文字数は、答案用紙の7割以上です。
採点の土台に乗るために最低限必要だからです。
専門記述では具体的な文字数に関する情報は公表されていません。
とはいえ、専門記述の採点をするのは、コンピュータではなく人間なので、当然見た目も大事になります。
明らかに字数が少ない答案は、採点官からの印象もよくないため、内容が良くても高得点は望めないでしょう。
なお、論文試験では、「1,000字以上1,500字程度と字数の指定があり、1,000字に満たない場合は採点されないことがある」と注意書きがあります。
1,000字は1,500字の約70%なので、「7割以上書かないと採点しない」とも言えるでしょう。
専門記述試験も同様の基準だと推測できるため、答案用紙の7割以上を埋めることが必須です。
>>【解決】都庁公務員試験の論文攻略ポイントと対策7ステップ【型が大事】
(論文試験の注意事項)
論文字数は、1,000字以上1,500字程度です。なお、論文字数が1,000字に満たない場合は採点されないことがあります。
東京都職員採用試験I類B 令和5年論文問題
合格ラインは3科目合計で平均以上
合格水準の目安としては、3科目合計で6割以上取ることです。
試験はあくまで相対評価であるため、平均より高い点数を取ればいいからです。
なお専門記述の具体的な合格ラインは公表されていないため、正確な指標はわかりません。
一方で教養試験は平均点以上が合格ラインです。
同様に考えると平均点を確実に超えられる6割以上が目安になります。
例えば、以下のような手ごたえであれば、平均点は越えられるでしょう。
- :準備していた模範答案を再現できた(80点)
- :内容に多少不足する部分もあるが、ほぼ模範答案を再現できた(60点)
- :内容に自信はないが、なんとか答案を埋めた(40点)
もちろん、3科目すべてを完璧に回答できるのがベストです。
しかし、実際に専門記述試験でパーフェクトに回答できる人はほとんどいません。
そのため、3科目合計で6割以上取ることを目指せばOKです。
まとめ:都庁の専門記述は5科目75テーマを準備して臨もう
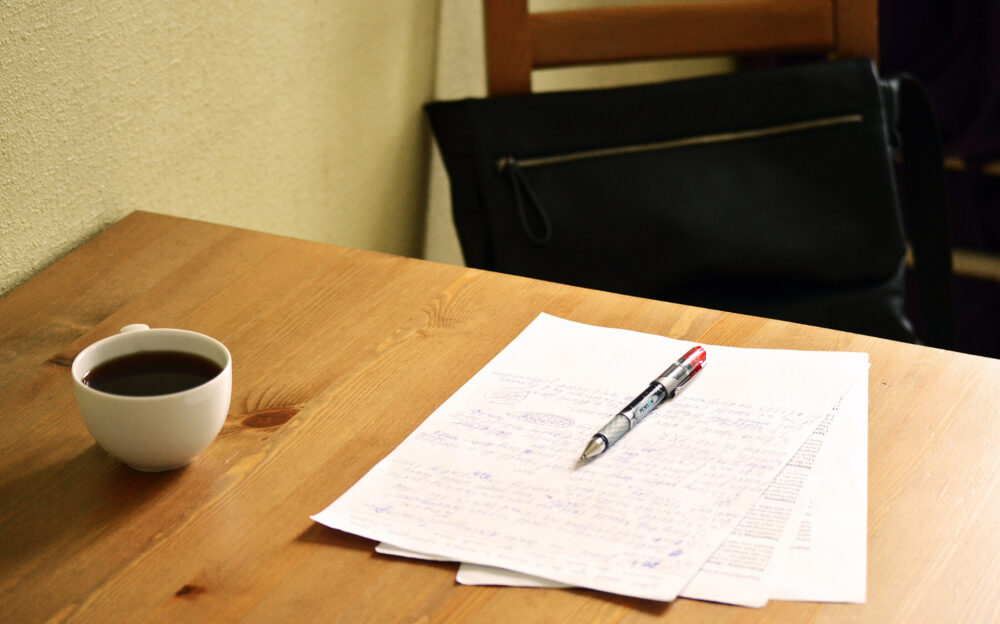
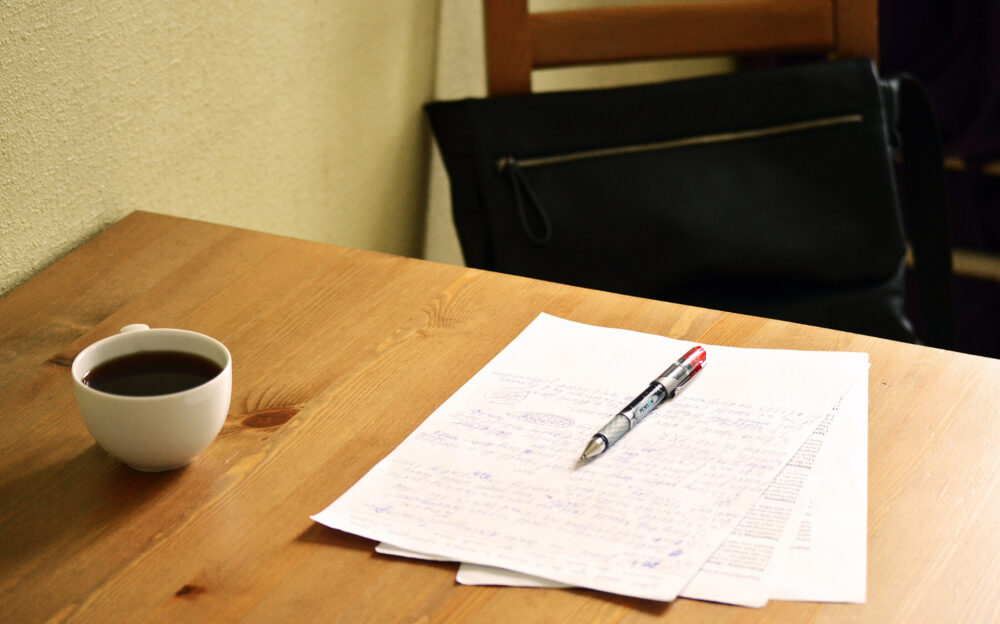
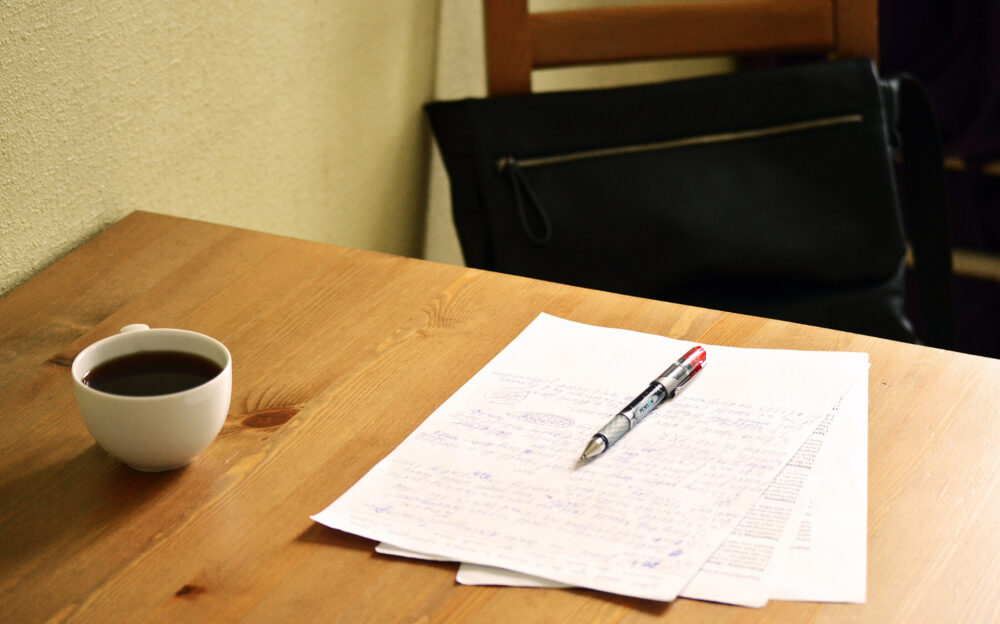
本記事の内容を確認します。
- 都庁の専門試験は5科目用意する
- 科目は各分野から分散して選ぶ
- 論点数は75題程度(各科目15題)準備する
- 出題テーマを予想して答案を準備する
- 試験当日は3科目合計で平均点以上を目指す
専門記述の試験対策は、覚えることが多く専門択一より大変に思うかもしれません。
しかし、実際は専門択一の方が科目も多く範囲も広いため学習に時間がかかります。
一方で、専門記述は科目も範囲もしぼれるため、択一と比較して学習負担は少ないと言えるでしょう。
とはいえ、着実に合格水準を満たせるように対策しなければ、最終合格はできません。
自分と相性の良い科目を選定して、準備万端のうえ試験にのぞみましょう。
今回は以上となります。ありがとうございました。